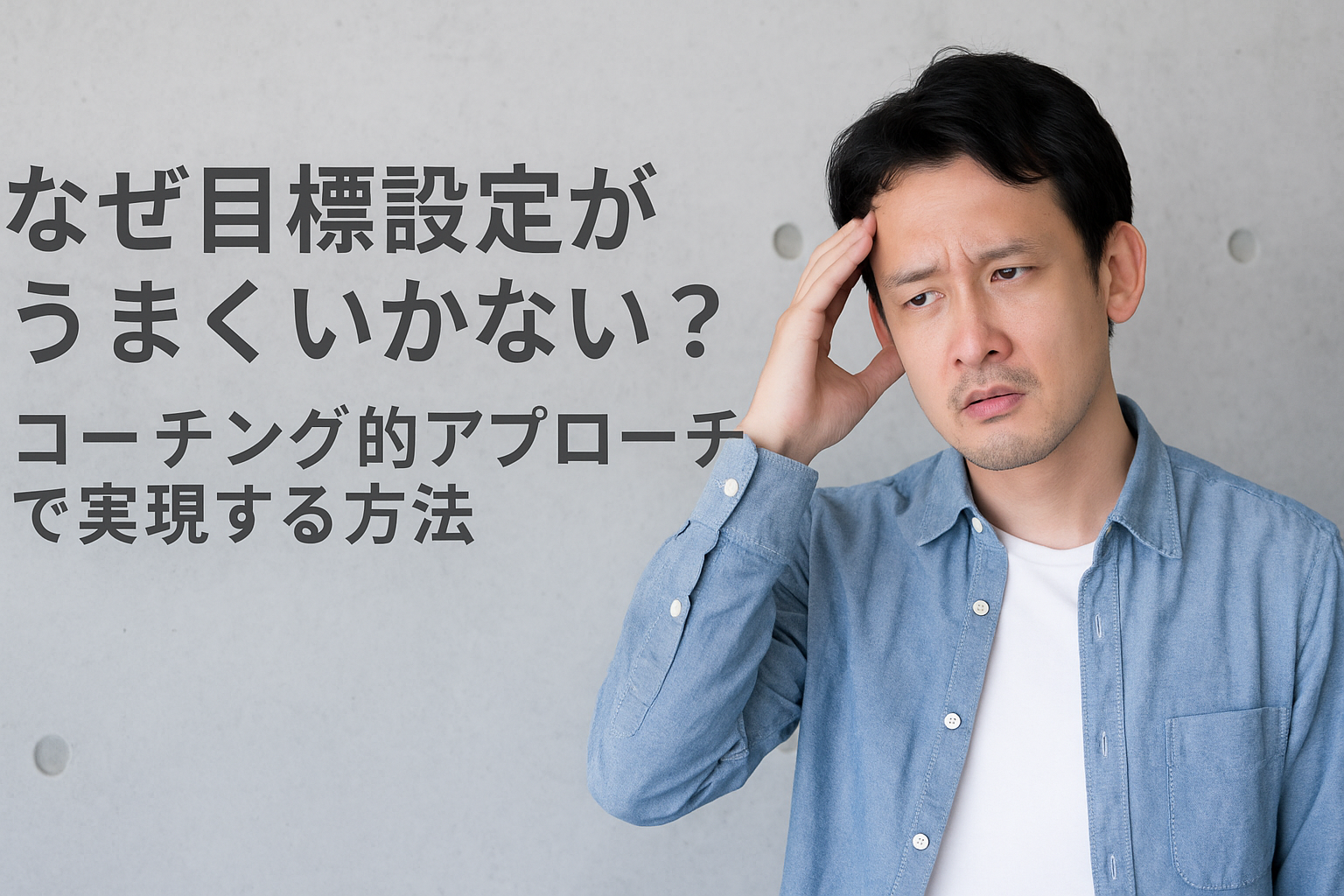立てた目標が、いつの間にか忘れ去られていませんか?
「今年こそ○○を達成する!」と意気込んで立てたはずの目標が、気づけば日常に埋もれてしまっていた──そんな経験はありませんか?
実はそれ、あなたの意志の弱さのせいではありません。多くの場合、目標の立て方そのものに原因があります。
私たちはつい、目標設定を「決意」や「根性」で乗り切ろうとしてしまいがちです。しかし、コーチングの視点では、目標はもっと柔らかく、そしてしなやかに設定するものと考えます。
この記事では、コーチングの視点から「なぜ目標設定がうまくいかないのか」を紐解き、実現性の高い目標の立て方をわかりやすくご紹介します。
あなたが「なぜ続かなかったのか」「どこでつまずいていたのか」の原因がわかることで、今度こそ実現に向けて動き出せるはずです。
なぜ目標設定がうまくいかないのか?
「本音じゃない目標」を立ててしまっている
私たちは、つい他人の期待や社会的な理想像に合わせた目標を立ててしまいがちです。
「これをやっておくと安心」「みんなやってるから自分も」「親や上司が喜ぶから」など、自分の内側から出た願いではない目標は、実行に移すエネルギーが湧きにくいのです。
たとえば、
- 「資格を取らなきゃ」→ 実はその分野に興味がないが、キャリアに有利と言われているから
- 「ダイエットしなきゃ」→ 健康のためではなく、他人の目を気にしているだけ
- 「SNSで発信した方がいい」→ 楽しめていないが、起業家っぽく見せたいから
こうした目標は、始める前からどこか重たく感じられ、行動に移すたびにストレスを伴います。
本音では望んでいない目標は、無意識のうちに「やらなくても困らない」と脳が判断してしまいます。その結果、先延ばしや中断が起こりやすくなり、自分に対する信頼感も下がってしまうのです。
本来、目標とは「こうなりたい」「これを叶えたい」と思ったときに自然と浮かんでくるもの。もし立てた目標に対して「面倒だな」「義務感が強いな」と感じたら、それは“本音”ではないサインかもしれません。
目標が「義務」になっている
目標が「こうしたい」ではなく「こうしなければいけない」と感じられると、それは義務に変わります。
「目標=やらなければならないもの」と捉えてしまうと、それは一気に苦しいものになります。
たとえば、
- 「〇月までに◯◯をやらなきゃ」
- 「できなかったら自分はダメ」
- 「失敗したら恥ずかしい」
こういった考えが先行すると、モチベーションはどんどん下がっていきます。
特に真面目な人ほど、自己否定とセットで目標を設定しがちです。「足りない自分を変えるため」「これができなければ価値がない」といった感情が強いほど、プレッシャーが大きくなり、心が萎縮してしまいます。
コーチングでは、目標は「自分を責めるため」ではなく「未来を広げるため」に使います。義務感から立てた目標は、たとえ達成しても心が満たされず、次の目標をまた義務として立ててしまう悪循環に陥ります。
その結果、達成しても喜びが少なく、失敗すれば罪悪感だけが残ってしまうのです。
目標設定の際は「これが叶ったら嬉しいな」と自然に笑顔になれるような内容かどうかをチェックしてみましょう。
達成イメージがぼんやりしている
目標を立てるときに、そのゴールのイメージが明確でないと、脳は「具体的に何をすればいいのか」がわからず行動に移せません。
たとえば、「収入を上げたい」という目標。 それだけでは漠然としすぎていて、
- 「どのくらいの金額を、どのタイミングまでに?」
- 「なぜ収入を増やしたいのか?」
- 「それが叶ったら、生活や気持ちはどう変化するのか?」 といった具体性が必要になります。
もし「月収30万円を40万円に増やす」という目標であれば、
- なぜ40万円なのか?
- そのお金で何をしたいのか?(家族との旅行、自己投資、貯金など)
- 増えた収入によってどんな感情が得られるのか?(安心感、自由、自信など)
このように「数字・目的・感情」の三点を明確にすると、目標は現実味を帯び、脳もそれを「重要な情報」として扱うようになります。
未来のビジョンがぼんやりしていると、私たちの行動は目の前のことで埋め尽くされがちです。「今は忙しいから」「もう少し落ち着いたら」と先延ばしするうちに、目標はすり減ってしまいます。
ゴールが明確であればあるほど、「今なにをすべきか」「なにをやめるべきか」の判断もしやすくなります。逆に言えば、目標達成に必要な行動がわからないとき、それは目標のイメージが不十分であるサインかもしれません。
コーチング的アプローチで目標を実現する方法
1. 「本音の願い」にアクセスする問いを使う
コーチングでは、目標を決める前に「何のために?」という問いを大切にします。
たとえば:
- もし何の制限もなければ、どんな毎日を過ごしたい?
- 今の自分に一番必要なことは何だと思う?
- 誰のために、その目標を叶えたい?
- それが叶ったとき、どんな表情をしている?
- その目標が叶わなくても、あなたの人生にはどんな価値がある?
こうした問いを通して、自分の本音と出会っていくことで、自然とエネルギーが湧く目標が見えてきます。
自分でも気づいていなかった「願いの種」が見つかったとき、目標は義務から希望へと変化します。
一度立ち止まって、「本当は何がしたいのか?」に耳を澄ませてみてください。
2. 感情を味方につける
感情は行動の原動力です。
目標を立てるとき、「達成したとき、どんな気持ちになっているか?」をイメージしてみましょう。
たとえば:
- 「家族と過ごす時間が増えて、心が安らいでいる」
- 「やりたいことに挑戦できて、誇らしさを感じている」
- 「もう自己否定せずに、自分を信じている」
- 「自分の人生に希望を持っている」
このように、感情のゴールを描くことで、途中で折れにくくなります。
目標そのものではなく、「その先にある感情」こそが私たちのモチベーションを支える燃料です。
毎日少しずつでも、その感情に触れられる行動を選ぶようにすると、やる気は自然と続いていきます。
3. 小さな成功体験を積み上げる
大きな目標ほど、一歩目を踏み出すのが怖くなりがちです。
そこで有効なのが、「小さな達成」から始めること。
例:
- いきなり「毎朝5時起き」ではなく、まずは「今日は10分だけ早く起きてみる」
- 「月収を倍にする」ではなく、「今月1万円の副収入を作るには?」
- 「毎日運動する」ではなく、「今日は1駅歩いてみる」
このように、すぐに取りかかれる小さな行動を設定することで、「できた!」という実感を積み上げていきます。
成功体験が積み重なると、自己効力感(やればできる感覚)が育ち、行動が加速していきます。それはまるで、自転車に乗れるようになる過程と似ています。
さらに、成功体験を「見える化」することで、モチベーションを保ちやすくなります。手帳に達成記録をつけたり、アプリで習慣を管理したりするのもおすすめです。
実例:コーチングで目標が動き出したAさんのケース
Aさん(30代女性)は、「英語を話せるようになりたい」という目標が、3年越しでずっと進まない状態でした。
初回セッションでは、目標が「やらなきゃ」から来ていることが明らかに。過去の挫折体験から、「勉強=つらいもの」という思い込みもありました。
しかし対話を重ねるうちに、「海外に住む友人と、心からの会話をしたい」という本音が見えてきました。
そこから目標は「TOEICの点数アップ」ではなく、「毎日5分、英語で日記を書く」に変更。ハードルを下げることで、取り組みやすさが格段に上がりました。
2ヶ月後には、自分の言葉で英語を話す楽しさを感じ始め、「英語を学びたい」という意欲が自然に湧くようになりました。
さらにその後、Aさんは英語学習を通して「自分の言葉で伝えることの楽しさ」に目覚め、職場でプレゼンを担当するようになったそうです。
目標の本質を見直すだけで、人生の方向が変わる──それを実感させてくれるエピソードです。
おわりに:目標設定は「自分との対話」から始まる
目標設定がうまくいかないのは、あなたの努力不足ではありません。
むしろ、「誰のために?」「どんな気持ちで?」という本質的な問いを見つめる時間が、これまでなかっただけかもしれません。
コーチングのアプローチは、あなたの中にある“本当の願い”を引き出し、それを実現へとつなげてくれます。
そして何より、目標は人生を制限するものではなく、人生を広げてくれるものです。
目標は「今の自分に足りないものを補う」ためではなく、「本来の自分の力を思い出す」ための道しるべでもあります。
今のあなたが「これだ」と感じる目標が、もしかしたら未来のあなたを導いてくれる道標になるかもしれません。
どうか今日、自分と静かに向き合う時間をとってみてください。そして、自分らしい目標を見つける旅に出る一歩を、そっと踏み出してみてください。